脳内物質オキシトシン研究の第一人者であり、脳や胃腸の分野で米国で最先端の研究を20年続けた「クリニック 徳」院長の高橋徳さんにお話を伺っています。
【医師と患者の対話ができていない】
私が最近危惧していることは、医師と患者との対話ができていない事、これは非常に問題です。

なぜできないかと言ったら現在の保険制度に一因があります。
現在の保険制度では、3分と30分の診察時間では、診療請求の点数は一緒なのです。
病院の外来診療は忙しすぎるので『一人の患者の診療に3分以上かけるな』このように病院から言われている先生方も少なくありません。
そうなると、医者は3分くらいしか診られない事態になってきます。
『胃が悪い』という患者さんでも話をよく聞いてあげると、実は『会社で怒られました』という話が出てきて原因がストレスだとわかったりします。
そのような場合、薬をすぐ出すのではなく、アメリカでは薬の代わりに瞑想やヨガなどの補完代替医療(Complementary and Alternative Medicine;CAM)を奨めます。
ヨガや座禅などの瞑想中にはオキシトシンやセロトニン濃度が上昇し、コルチゾールやアドレナリン濃度は低下します。
視床下部から分泌されるオキシトシンが不安やストレス反応を抑制する作用があることが解っています。
日本もこんなことを説明して、ヨガや座禅などを奨める医者が増えたらいいなと思いますが、一人3分の短い診療に追われているわけですから、難しいでしょうね。
大学の心療内科の先生方もそのような新しい考え方を持っていただきたいと願っています。
【薬漬け医療の元凶】

現代医療は薬剤に依存しすぎている傾向があります。その原因には、製薬会社がお医者さんにうまく取り入って、薬を処方してもらっているという一面もあるかもしれません。
もうひとつ、日本には特殊な事情があります。厚生労働省の官僚の天下り先がほとんど製薬会社なんです。
こんな記事があります。https://www.yakuji.co.jp/entry20454.html
6年程前に、厚生労働省は、同省や国立病院機構に在職歴のあるOB29人が、国内の主要製薬会社15社に再就職していたとの調査結果をまとめ、公表したことがあります。
調査は、長妻厚労相の指示で行われたもので、日本国内の主要な医薬品メーカーの協力を得て、医薬品メーカーに在籍する者のうち、厚労省または国立病院機構に在職歴のあった職員の実態を調べたのです。
その結果、29人のうち、本省内部部局の職員7人、国立病院の医師等12人、施設等機関の研究員等(検疫所、国立感染症研究所)3人が製薬企業に再就職していることが判明したのです。
残りの7人については、退職時の所属について回答がありませんでした。
この結果を受け長妻厚労相は、1996年に定められていた「製薬企業への再就職の自粛」を再徹底させるよう指示したのです。
ところが、この自粛勧告が現在も機能しているかどうかは、疑問の余地があります。
厚労省官僚の製薬業界への天下りが、日本の医療行政を歪めている可能性を危惧します。「薬漬け医療」の元凶には根深いものがあるように感じています。
『週刊現代』の薬のインタビュー記事について

以前、『週刊現代』の(2017年9月4日発売)に私のインタビュー記事が載りました。
内容は、医療記事アンケートで「自分では飲まない薬」というものでした。
そこで私は以下のように答えました。
薬名【鎮痛薬:リリカ】
この薬は現在、整形外科ではいっぱい処方されています。
ロキソニンやバファリンとか昔ながら使っている鎮痛薬があるのですが、実際、慢性の痛みには効かないのです。
ただ今までは鎮痛薬といえばこれらしかなかったので、これらがずっと処方されていました。
そしてリリカが4~5年前にでて、整形の医者が喜んで使うようになり、どんどん処方されています。しかしこれは理論的にも、臨床的にも効きません。
アラキドン酸からプロスタグランデインができます。アラキドン酸からプロスタグランデインを抑える薬がロキソニンやバファリンです。
急性の痛みは末梢組織からでたプロスタグランデインが神経を刺激して痛みの信号が中枢に届き痛みを感じます。これが急性の痛み。
お年寄りの痛みというのは腰が痛い、膝が痛いなど、慢性の痛みがほとんどです。これはまた別問題であり、プロスタグランデインは末梢組織で増えていません。
慢性の痛みというのは知覚神経が異常に興奮している状態です。これが慢性の痛みの原因です。
そこで、異常に興奮した知覚神経を抑えるという発想でリリカが開発されました。
ただ残念ながらリリカは知覚神経のみならずいろんな神経の活動も抑えてしまいます。つまり神経全般を抑えてしまうのです。
神経には痛みを伝達する神経(知覚神経)もあれば、痛みをブロックする神経もあります。痛みをブロックする神経というのはいわゆる脳内麻薬(オピオイド)です。
リリカはこの脳内麻薬も抑えてしまいますから、痛みを伝達する神経(知覚神経)を抑える一方で、痛みをブロックする神経も抑えます。
したがって、プラスマイナス0となり、痛みに効かないわけです。理論的に当たり前の話です。
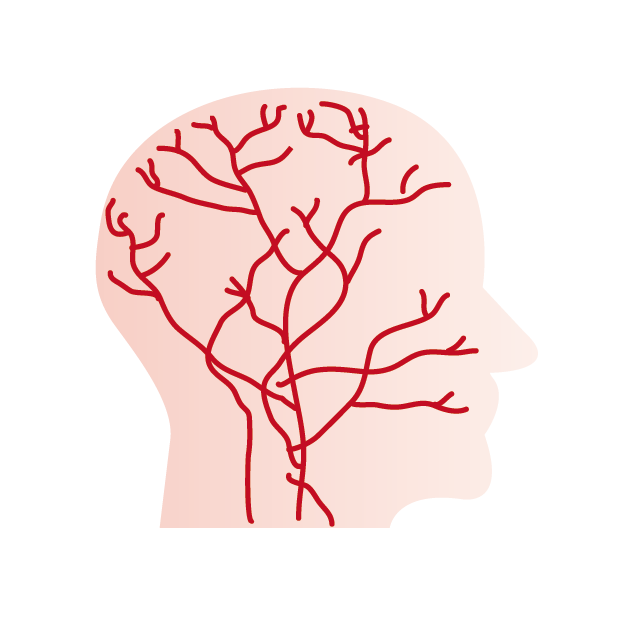
それに神経活性をすべて抑えてしまうので、意識や思考、記憶などの大脳の高次機能も抑制してしまいます。リリカとはこのような薬です。
どこかの偉い大学教授がリリカは25mgから始めて効かないなら、50、100、そして150mgまで投与してもいいと言いました。
そしたらもう患者さんはフラフラです、運転できません。このような事も起きてしまいます。まさに『百害あって一利なし』です。
薬名【痴呆症薬:アリセプト】
アリセプトはある製薬会社が作っていますが、その製薬会社のホームページに、飲み始めて6ヶ月の間でプラセボ(偽薬)に比べ痴呆の進行度が減少しているというデータが掲載されています。有意差もあるので、アリセプトは認知症に著効するとされています。
しかしアメリカでも試験が行われておりメイヨークリニックでの500人を対象にした3年間の追跡調査では、アリセプトとプラセボの間には、その進行度に差がなかったと報告されています(2005年)
すなわち、アリセプトが効くのは最初の半年だけで、3年間飲み続けると、プラセボ(偽薬)を飲んでいた人と同じ程度の認知障害になるということです。
もっと端的にいえば、アリセプトを飲んでも飲まなくても、同じように認知症は進行するということなんです。
製薬会社もこの事実は知っているとは思いますが、メイヨークリニックの論文の結果は会社のホームページでは言及していません。そして残念ながら、アリセプトを処方している現場の医師でこの論文を知っている者はごくわずかです。
ある市民病院の内科の先生が、認知症の治療について開業医む向けのセミナーをされたことがあります。
その先生はアリセプトを多く処方されていたので、その先生にセミナーのあとで質問してみました。
『確かにアリセプトが6ヶ月以内では効果があるようですが、メイヨークリニックが2005年に250人ずつでプラセボと比較した臨床研究を行なったところ、3年経ったらプラセボとその進行度は一緒だった、という論文があるんですけど、この結果をどうお考えですか?』
すると、その先生は『すいません、不勉強でよく知りません。』と答えました。
日本の医者は英語の論文を読むことは少ないと聞きます。ではどこで勉強するかといえば薬屋さんから学ぶのです。
薬屋さんが自分たちの製品に不利なデータを医者に説明することはありえないでしょう。医者が詳しい薬理作用を知らない事も少なくありません。
かくいう私も若い頃は、薬理作用についてあまり調べもせずに、やみくもに処方していた時があります。
薬名【骨粗鬆薬:ビスフォネート系薬剤】
この薬は骨密度を上げるために安易に処方されています。普通だと古い骨細胞は死んでいき新しく若い骨細胞ができてきます。
しかしこの種の骨粗鬆薬は骨代謝を抑えてしまうので古い骨細胞が生き残ってしまいます。
古い細胞が生き残るとどうなるか?古い細胞が死なないわけですから、骨密度は高くなるでしょう。
しかし残念ながら、骨代謝は抑制を受けていますので、若い細胞が生まれてこなくなります。
骨はある程度、柔軟性があるから折れないんです。骨粗鬆薬を投与すれば、骨密度は増えてくるかもしれません。
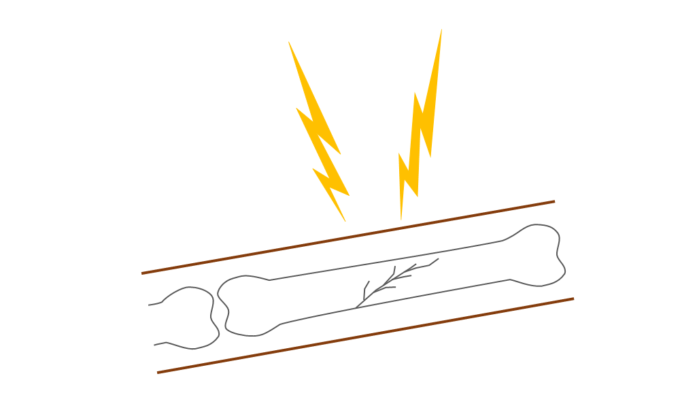
ただカチカチに硬くなってしまうので折れやすくなります。そのため、顎骨壊死や骨幹骨折など重大な副作用が起きることがあります。
顎の骨はそんなに強い骨じゃないんですが、毎日、毎日食事のたびに噛んでいるので使う事が多いです。それで負荷がかかるから壊死してきます。
したがって、歯医者さんは骨粗鬆薬を服用している患者さんの治療には、大変な気苦労をします。
お年寄りが転ぶと大腿骨の頚部が通常は、骨折します。ところが骨粗鬆薬を飲んでいると骨が硬いので大腿骨の真ん中で折れてしまいます(骨幹部骨折)。
これは普通ありえない事なので、この現象を英語で Funny Fracture (おかしな骨折)といいます。
Funny Fracture —なんとも自虐的な表現で笑ってしまいますがー この言葉は骨粗鬆薬の副作用の項目にちゃんと書かれています。
薬名【高コレステロール血症薬:スタチン剤】
頸動脈エコーで所見がなく、血中コレステロール値が250 mg/ml以下であれば、私はスタチン剤を処方しません。
血中コレステロール値を220mg/ml以下に下げるべく、スタチン剤などが一般的に処方されていますが、副作用が多岐にわたるため、慎重投与が望ましいと考えています。
一方で、コレステロール値が240~250mg/mlの人が一番長生きできるという皮肉なデータもあります。
薬には副作用がつきものです。まずは、患者さん側も勉強して知ることが大切です。
普段、私が患者さんに見せている副作用が調べられる便利なサイトがありますので、皆さんも是非活用してください。
【関連記事】
医療・福祉の現場でも注目が集まる心のケア「ロボット・セラピー」
自律神経を整えてストレスをなくす幸せホルモン「オキシトシン」
五感に心地いい刺激を与えることで体の不調を改善【補完代替医療】

高橋徳(たかはし・とく)
1977年、神戸大学医学部卒業。関西の病院で消化器外科を専攻した後、88年米国にわたる。ミシガン大学助手、デューク大学教授を経て、2008年よりウィスコンシン医科大学教授。
米国時代の研究テーマ「ストレス」を研究していく過程で、オキシトシンと出合う。以降、10年以上にわたりオキシトシンの研究を行い、アメリカでオキシトシンに関する論文を発表。
帰国した後、国内のオキシトシン研究の第一人者として、日々研究を続ける。
13年には、郷里の岐阜県で統合医療クリニック「高橋医院」を開業。
16年、名古屋市に分院「クリニック徳」をオ—プン。
主な著書に、『人のために祈ると超健康になる! (米国医科大教授の革命的理論)』(マキノ出版)『自律神経を整えてストレスをなくす オキシトシン健康法
』(アスコム)『人は愛することで健康になれる (愛のホルモン・オキシトシン)
』(知道出版)、『あなたが選ぶ統合医療: 古今東西の叡智が命を守る
』(知道出版)。
養生ラボ編集部です。インタビュー取材、連載コラム編集など。

