看護師や療法家を含む医院・施設専属のクリニカルアロマケアチーム タッチケアサービスさんによる連載コラムです。
中医学視点から観るアレルギーと産後
月1回の産後ケア連載コラム。今回5回目となりました。
前回【産後のメンタルとは?】に引き続き、中医学視点からのお話になります。今回は、現代人に多いアレルギーのお話と産後ケアのお話に繋げていきたいと思います。
蕁麻疹・鼻炎・喘息・結膜炎・花粉症・アトピーなどの代表的なアレルギー。
年齢・男女問わず、また産後に限らず、幅広く私たちの身体に影響を及ぼしているもので、今の日本では現代病の一つといっても多言ではないでしょう。
戦後、高度成長期と共に昭和30年代後半~40年代ぐらいにかけて、日本にアレルギーが増加しつつ、現在に至っているようです。
昔に比べ、手軽に美味しく食べられる物が増え、食べる時間や量や質が自由に選択ができる便利な時代となりました。
食べ物は口から入り胃腸で消化吸収されます。
中医学視点でも臓腑(五臓六腑)の一部である脾胃(胃腸のイメージ)が食べた物を消化吸収し、それぞれ必要な臓腑に行き渡って人の身体の生きる源を作っていると考えます。
脾胃は後天の源(いのち)を作る重要な工場であるため、人の身体を観ていく時は胃腸の状態を確認することは重要です。
脾胃(胃腸)は食べ物が豊かになったおかげでフル稼働。休みなく働かせられている感じ。まさに過酷な労働条件。
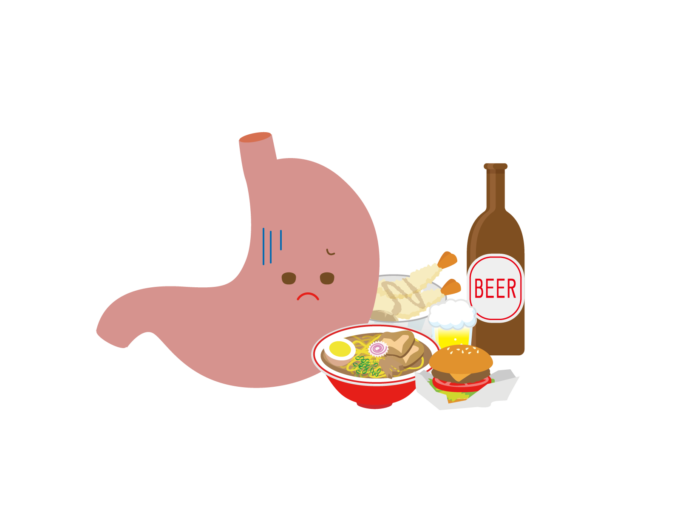
これを身近な例えでいえば、勤務時間以外に休日関係なく残業をずっとさせられている状態。休みがない状態。そうなるとどうなるでしょうか?
体調を崩したり、最悪の場合過労死に繋がることもなりかねません。まさに今の私たちの胃腸はそういう状況なのです。
そうすると胃腸はストライキを起こすことになり、免疫力(中医学では、『衛気』といいます。)が低下し、結果としてアレルギーという形で私たちにアピールするようになります。
(もちろん、原因はこれだけに限らず、他にもきっかけはあります。)
人が夜になると寝て身体を休めて、次の日、頑張れるように、胃腸にも休める時間が必要なのです。
一日3食栄養をしっかりとること、食べることももちろん大切なことです。
しかし胃腸の働く都合も聞かず、いいものだからといって、常に食べ物を胃腸に流し、胃腸を働かせ続けることはいいことでしょうか?
胃腸の都合というものもあるのです。その都合は個々違うのです。
『腹八分目』という言葉があるように、ほどほどというバランスが大切です。
中医学では、その胃腸の状態を知ることでその人に合ったバランスを考え、養生もケアもできるのです。
そして産後の身体は出産という大仕事の後、気血精(脾胃で作られます。)が消耗中。
寝不足や授乳が続くことによってさらに気血精を消耗。それを作りだすのに脾胃は必死に働きます。
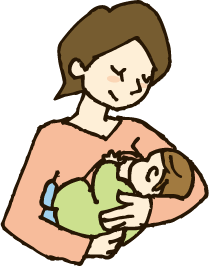
まさに胃腸の元気不足(気虚)になりがちの状態(気虚の度合いに個人差があります。)
そういう時、体力をつけなくてはならないからといって、気血を作りだすためにと必要以上にたくさんの食べ物を選ばず何でも食べることは危険です。
その時々の胃腸の都合に耳を傾けながら、食べる物の『質・量のバランス』を考えていくことが養生の一つになっていきます。
産後に限らず、くれぐれも冷たい食べ物・飲み物はなるべく避けてほしいものです。
冷たい物は胃腸にムチを打つようなもので、余分な水分が胃腸に停滞しやすくなり、冷えや湿気を増やし、代謝を低下させ、2次的な病因を起こしかねないからです。
そして、産後の元気不足になっている胃腸をサポートするきっかけの一つにアロマトリートメントはとても合っていると思います。
胃腸をケアするにもアロマの香りによって気を巡らすきっかけになり、人の手による温もりのある優しいタッチングによって身体は緩み、衛気力が高まり、同時に胃腸が動き出してくれます。
タッチケアサービス講座・中医学担当 山口恵美
【関連記事】
アロマトリートメントで睡眠の質を高める【産後のメンタルとは?】

タッチケアサービス
看護師や療法家を含む医院・施設専属のクリニカルアロマケアチーム。出産直後の患者、延べ15.000件以上の症例等を保有。
西洋医学・東洋医学両視点からのケアを深めるための講座を開催。現場に則した内容の講義講座や勉強会を行う。
クリニカルセラピストを目指す方、セラピストとして学びを深めたい方、また各療法家、医療従事者すべての方が対象で理論だけにとどまらず実践的かつ専門的に学んでいる。
また、様々なかたちで生活に取り入れやすいホリスティックライフ実践のための提案・ケアを一般対象にも行っている。
【touch care services lesson】
産院専属セラピストチームから産後ケアを学ぶ、年4回のホリスティック産後ケア講座開講中
詳細・問い合わせはタッチケアサービスHPまで → http://www.touchcare-s.com
養生ラボ編集部です。インタビュー取材、連載コラム編集など。



